昔の日本には『完全』をよしとしない考え方があったそうな。
『完全』は終わりの始まりだからだそうです。
それをいいことに
完璧には程遠いガイドである私が
不完全であることを逆手にとって前面に出しながら京都のガイドをするシリーズ
今回は『梨の木神社』です。
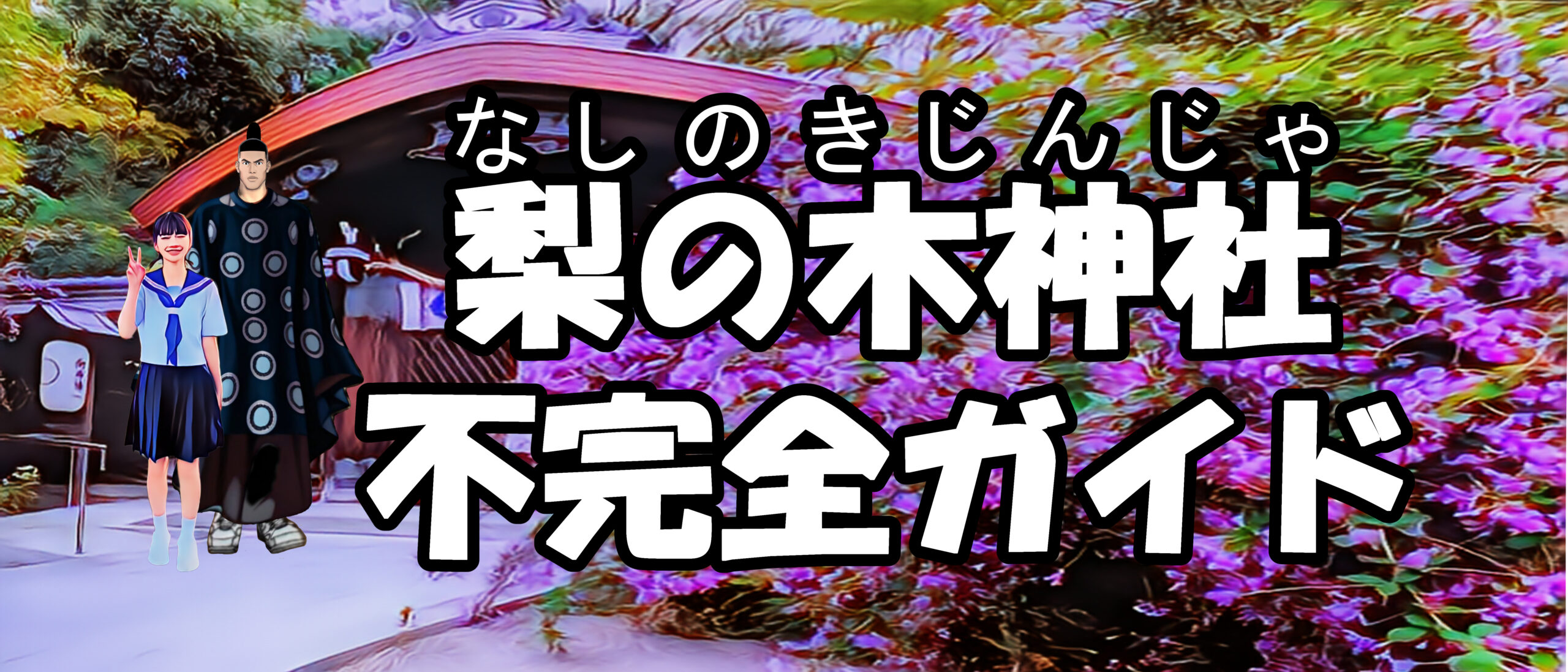
外国からのお客様の中には
神社と仏教寺院の見分けがつかないとおっしゃる人がいらっしゃいますが
この画像のような

二本の柱のてっぺんあたりを二本のはり(梁)でつないだ『とりい(鳥居)』と呼ばれる門のようなものがあれば神社です。
この鳥居は梨の木神社の鳥居
梨の木神社では
少しだけオリジナルな
私達バリアフリーツアー京都流の神社の楽しみ方をご紹介したいと思います。
※時短がいい人は動画をよかったらどうぞ
参道の意味

まず
梨の木神社のまっすぐな参道をごらんください。
まっすぐな参道には意味があります。
『いい神』が祭られているという意味。
曲がっている参道の神社もあります。

京都で言えば『北野天満宮』がそう
『疫病神』が祭られているという意味
北野天満宮に祭られているのは日本最強の疫病神の一人
天神『菅原道真(すがわらのみちざね)』

※神道では神を数える単位は柱ですが専門用語をむやみに使うのは初めての人にやさしくない気がして私はあえて必要ない場面では使いません

なぜいい神だけでなく悪い神まで祭るのか?
これは神道の作戦。
神道には
いい神を祭りいい神をさらに強力でいい神にうつろわせ
悪い神をも祭り悪い神をもいい神にうつろわせ
ヒトにとっていいこと(ご利益)をもたらしてもらう作戦が流れています。
すべてがうつろうことが前提の昔の日本人らしい作戦。
千年以上前から遂行中のこの作戦に参加することが観光というエンタメにつながります。
でも
祭るって具体的に何をするのか?
祭ることの本質を知らないと作戦にも参加できませんし神もうつろわないしご利益ももらえません。
私自身が『祭る』を理解するのに役立った、説明がわかりやすくて面白いある宮司さんの言葉をそのまま使わせていただきます。
その宮司さんの神道の世界観では
ヒトは肉体が滅びて魂になっても自己承認欲求だけは残るんだそうです。
神も同じ。
祭るとは神が自己承認欲求を満たすお手伝いをすることだそう。
一般の参拝者の方には
自分のお願い事だけ言うのではなく
お願い事を言う前に神の自己承認欲求を満たすような言葉を添えて等価交換してほしいそうです。
神の「ほしいもの」とあなたの「ほしいもの」の交換。
具体的には
「あなたはすごかった」
「感銘をうけました」
「尊敬しています」
「大好きです」
「あなたがこの世界にいてくれてよかった」
などど「推し」にかけるような言葉を添えるイメージでいいそう。
私は「なるほど!」となりました。
これは『愛でる』です。つまり『もののあわれ』
もののあわれ
時短でゼロから説明しますね。
日本には古代からもののあわれの文化が流れています。
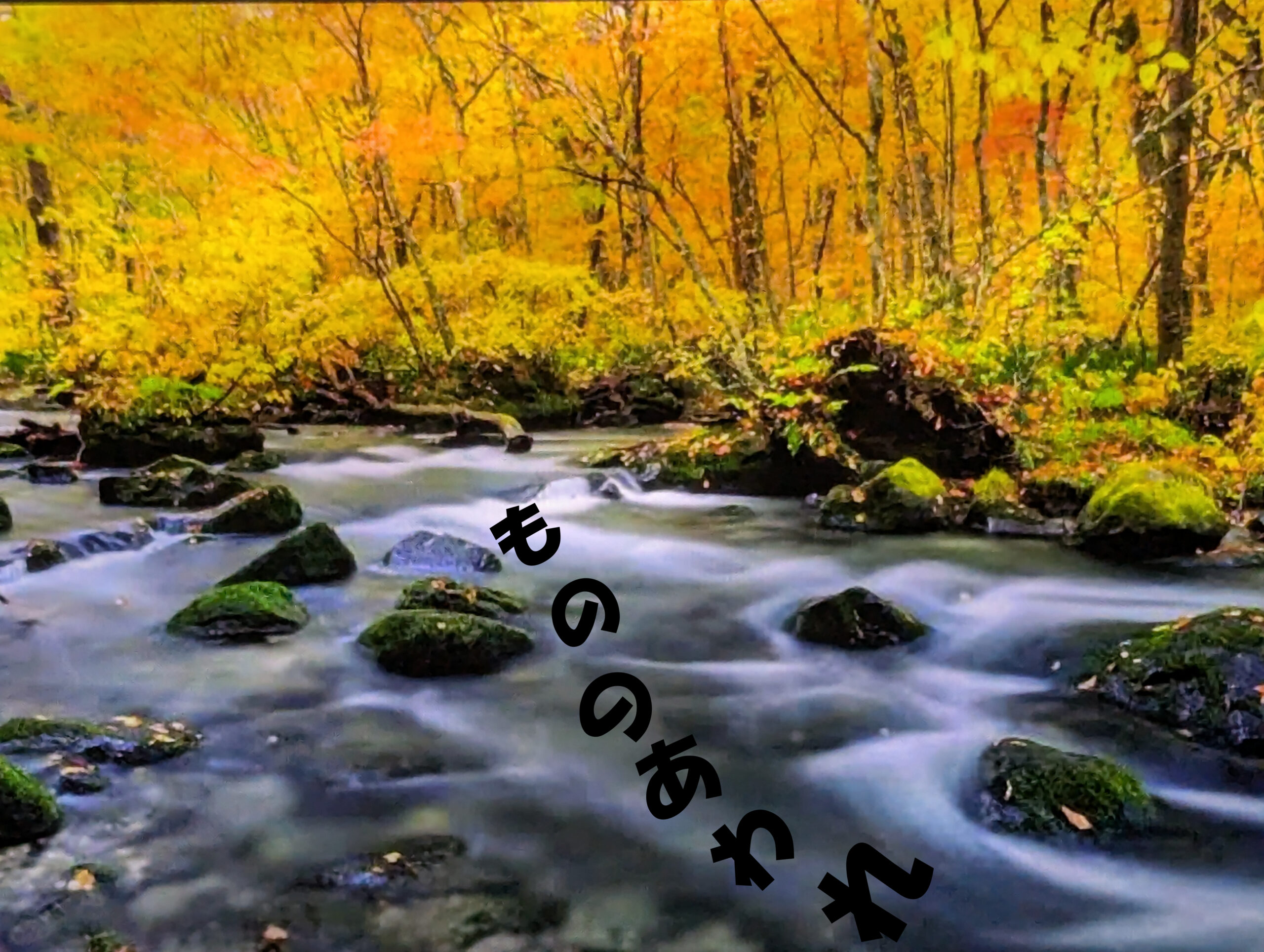
翻訳から入るとわかりやすいです。
「もの」はぼんやりとすべてのもの。英語でいうとanything
「あわれ」は「うっとり」 もう一段階翻訳して『愛でる」
「もののあわれ」はいやなものをも含む「すべてのものを愛でる」という意味です。
神道では疫病神をもふくむ無数の神を祭りますがそれが
私の中でもののあわれにつながりました。
もしかしたら神道の作戦のほうが古くて『おおもと』なのかもしれません。そのへんはいちガイドが断言できるものではありませんがそう考えたほうがしっくりとくるとだけ言っておきます。
では、「祭る」の正体は「愛でる」とふまえて梨の木神社の神を愛でに行きましょう。
※さしあたり、観光を楽しむのには上記の知識だけで大丈夫だと思いますが『もののあわれ』をもっと深く知りたい方はよかったら動画をどうぞ
境内へ
これ以上ないくらいに真っすぐな梨の木神社の参道

これ以上ないくらいに「いい神」が祭られていると考えて安心して境内に入りましょう。
曲がった参道の神社に入る場合は少しゾクっとしながら入りましょう。でもそんなに怖がる必要はないです。長い時間祭られていい神にうつろっているはず。北野天満宮の菅原道真も今では最強の学問の神様にうつろっています。ご安心を♪
※ちょっと脱線
ただ、私も大好きな芸人さんでこの世の不思議なことを体当たりで長年追い続けてきた「北野誠(きたのまこと)」さんは、「山奥の何が祭られているかわからない神社や、誰も長年参拝していなさそうで宮司さんもいない廃神社に遊び半分で行かんほうがいい。神なめたらアカン!おまえら行くな」とおっしゃいます。さっきの宮司さんの話に照らし合わせてみて私もそう思います。疫病神は長時間たくさんの人に愛でられていい方向にうつろうのですから、長時間放置され誰にも愛でられていない神は、もともといい神でさえ疫病神にうつろってしまっている可能性があると推測できます。
神がいいほうにうつろうためには愛でられることが必要。この視点で見ると神道の参拝作法はよくできています。
神道の作法
神道の参拝の作法は神の自己承認欲求を満たすための作法です。
礼も拍手も手や口の清めも
すべての動作が神への敬意
型にはまらないガイドの私が言うのもなんですが
神をちゃんと愛でてうつろってもらうため
また
等価交換が成立しご利益をもたらしてもらうため
もっと言ったら
神とウインウインになるため
ここは
ひとつひとつの動作が「尊敬表現」の意味をもつ神道の作法の型にちゃんとはまりましょう。
まず鳥居の前で一礼。
参道の真ん中は神の通り道。真ん中はあけて日本では左側通行が習慣なので画像の矢印のイメージで境内に入ります。

すると雰囲気が変わります

見えない何かを感じる文化

神道の本質は「見えない何かを感じる文化」です
ここ梨の木神社も、
私の脳が作り出したストーリーなのか
作庭家の演出なのか
はたまた本当に見えない何かが存在するのか
私にはわかりませんが
確かに雰囲気が変わります。
おそらくこれが見えない何かを感じているという状態
そしてこの本質がそのままエンタメに転用可能。
変わる雰囲気を楽しみましょう。

~♪
※ちょっと脱線
前回の祇園祭りの時
八坂神社の宮司さんが特別観覧席でのお酒の提供に反対されました。
理由
「心静かに神を感じてほしい」とおっしゃってました。
賛否両論でした。
ガイドの知識として神道の本質が「見えない何かを感じる文化」だと知っていると
この宮司さんの言葉
本質を大事にしようとしている気がして結構ささったんですけどね。
清め
神道にとって「清め」は重要な概念。
参拝作法としては、

手水舎(てみずや)で手と口を清め

参道にそって境内に敷いてある玉砂利の上を通ってはきものの泥を落とす
などがあるのですが
コロナパンデミック以降、神社側も無理にしなくていいという感じになっています。
実際、手水舎も玉砂利も衛生環境が今よりもずっと悪い時代の知恵なんですよね。
合理的に考えると
今は道はアスファルトで靴に泥がついているような人はあまりいませんし
現代人はことあるごとに手洗いうがいをします。
おそらく千年前の参拝者が手水舎や玉砂利で清めた後よりも科学的に清潔です。
神に対して失礼なほど不潔ではないとみなせます。
なのでガイドとしても無理にお客様にすすめるようなことはしません。
ただ
形式美は日本文化の特徴のひとつ。
そこを楽しみたいかたは手水舎や玉砂利で清めてもらってもちろん結構ですよ♪
垣間見の技

いい枠がありますね。
「垣間見の技」を使いましょう。
垣間見の技とは
枠で切り取って対象物を見る技。
門や鳥居は垣間見の枠として使用できるように作庭家が設計していることが多いです。
コツをひとつだけ
「昔の人の目の位置を意識」
昔の人は今の日本人よりも身長低いです。
ここ梨の木神社の場合も少しだけ膝を曲げたりかがんだりしてベストポジションを探ってみてください。
行きますよ。
垣間見の技発動
垣間見の技発動


うまく垣間見できましたか?
では拝殿へ。
※観光を楽しむのには上記の知識で充分。ですが垣間見の技をもうちょっと深堀したい人はよかったら動画をどうぞ。
主祭神
愛でるといっても
神のことを知らないと愛でにくいです。
予備知識ゼロの人にもわかるようにご紹介します。
梨の木神社の主祭神は三条実万(さねつむ)さん

ひとことで言うと
さねつむさんは「ブレない能力」の持ち主。
さねつむさんは150年前の人。
150年前の日本は
みんな日本の未来のことを心配したからなのですが
いろんな意見が対立した時代。
違う意見の人の迫害もおきました。
さねつむさんも迫害されます。
が
さねつむさんはけしてブレませんでした。
死の危険にさらされてもブレませんでした。
これも「もののあわれ」で説明できます。
さねつむさんともののあわれ
ヒトの本能は死をいやがりますが
本能がいやがるものをも含むすべてを愛でる「もののあわれの技」の使い手の昔の日本人は
死をも愛でようとします。
死の中でもたいせつなもののための死は
美しい
名誉
本望
だとか設定し
このストーリーを時間と回数をかけて信じ切ることにより
本能の上書きに成功します。
さねつむさんは武士ではなく貴族ですが
「武士道とは死ぬことと見つけたり」の武士の考え方もさねつむさんのような貴族のブレない魂ももののあわれで説明できます。
さて
そんなさねつむさんのブレない能力にあやかりたい人は愛でる言葉を添えてお願い事をしましょう。

神を愛でる
神を愛でる作法は二礼二拍手一礼。全神社共通です。
※二礼二拍手一礼が初めての人は動画をどうぞ
神を愛でる言葉を添えてお願い事
神にもいい方向にうつろってもらい
お客様もいい方向にうつろいましょう
現代科学も昔の日本人も言うように、
すべてがうつろうのですから
可能性はあります。
最後に賽銭の金額について
賽銭
「いくらがいいの」とお客様に質問されることがあります。
ここは本音トークで行きます。
いろんな意見があります。
金額が高いほうがお願いごとがかなう確率が高いと本気で言う人もいますし
願掛けは神との契約なので、お願いごとが叶ったらどうするか、たとえば神社に寄付をするなどと、最初の願掛けの時点でちゃんと約束してそれを必ず守らなければならないと言う人もいます。
契約を守らなかったせいで恐ろしいことが起こる怪談まであります。
でも
少し変わった角度から物事を見るくせのある私から見れば
これは〇〇側の作戦です。昔から怪談って人をある方向に誘導するために作られることもありますしね。
でもまあまあまあ
拝観料を取らない神社の経営が困難だとはよく聞きますし神を祭る神社が潤うことは間接的に神を愛でることにもつながると思うので私もいつも賽銭多めには入れているつもりです。特に、好きな神や神社には。
金銭的に余裕のある人はいろいろわかった上で多額の賽銭や寄付をするのはありだと思います。
が
先ほどの宮司さんの話に照らし合わせてみても
魂となった神に残された欲求は自己承認欲求だけですから
金銭欲求は無いと考えられます。だって自分は使えませんからね、、、。
たいせつなのはやはり神を愛でること。これしか神はほしくないはず。
以上のことをふまえて出した私の結論は
『賽銭は五円玉』
日本に昔からある言霊信仰です。
言霊信仰
言霊信仰とは「言葉には現実を引き寄せる力がある」という考え方。
日本人は賽銭は五円玉を使う人が多いです。
神と五円(ご縁)が結ばれるという未来を引き寄せようとする言霊信仰。
これを
神の視点で見てみましょう。
視点逆転の技『みすず』発動


ガイドとしてはいつも念のためお客様全員分の五円玉をそろえています。
ちょっとだけ手間です
が
多くの料理人が言うようにひと手間かけることは愛情
神を愛でることにつながりませんか?
それに
どうですか?
神の目線で↑の画像を見ると
「あなたとご縁を結びたい」という言霊をのせて
ひと手間かけてちょっときれいめな五円玉をちゃんと用意して
あなたを承認してくれる言葉を添えて願掛けをしてくる参拝者は
かわいいと思いませんか?
日本文化「かわいい」の正体はどうやら「近づきたいと思わせる何か」
神道の神も元ヒトです。かわいいと思ってくれて接近してくれる可能性が上がるのではないでしょうか
以上の事をふまえて
いろんな意見があるのは承知の上で
ハッキリひとつだけを示してほしいお客様のために
私達バリアフリーツアー京都では「賽銭の額は五円」を正解とします。

では あなたの観光がいいものになりますように
そうそう
帰り道も参道の真ん中はあけて通行
鳥居を出たらふりかえって一礼を忘れずに
ここまで来たら最後まで神を愛でる形式美を貫きましょう。
そしてついでにお別れの『垣間見』発動


